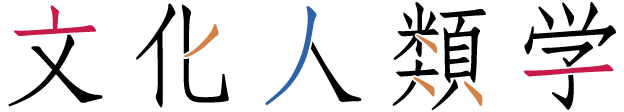しゃべり場
下戸in飲みニケーション
皆さんご無沙汰しております。2024年3月修了生の寺本です。
社会人として歩みだしてからようやく1年がたちました。私にとっては長い長い1年でした…。久しぶりに訪れたしゃべり場で、懐かしい面々を含んだ研究室メンバーの様子を垣間見て心が癒されました。
私は現在、大学の事務職員として経営に携わる部署に配属されて働いています。(熊大ではありません)
とてもざっくり言うと、私の部署は大学が行うべきプロジェクトや取り組みを考える部署で、私は下っ端として日々勉強しています。
この仕事では、様々な部署の人と話し合い、お互いの妥協点や合意できる点を探ることが求められます。そこで重要だと実感したのが「共食」です。私は文化人類学を学ぶ中でこの「共食」をキーワードに研究していました。文字通り「共に食べる」ことを主に意味し、これを介して生まれるつながりがある、と私は考えています。
社会人にとって身近な「共食」といえば、飲み会です。私はこの1年でたくさんの飲み会に呼んでいただきました。実は私は超が付くほどの下戸(ほろ酔い1缶も飲みきれません)なのですが、面白そうだと思って、お誘いいただいたほとんどに参加しました。そこでは、いわゆる「飲みニケーション」が繰り広げられているのを見ることができました。
私が参加した飲み会はどれも各々の好きな飲み物を楽しんでいました。酔いが回ってくるとテンションが高くなり饒舌になる人も多いですが、こちらも負けじとお喋りになれば場の勢いから置いてけぼりになることはありませんでした。料理をきっかけに業務時間には話せないことで会話が盛り上がって、仕事の場面では聞けなかったかもしれない本音などを聞くこともありました。こうした話で盛り上がることで、「ここに居るのは食事を共にし、話して打ち解けた相手」というつながりの意識が生まれていました。
この飲みニケーションの効果は、私が思っていたよりもずっと長く期間続くものでした。1回飲み会で顔を合わせただけの人と仕事の場面で再会した際、一度は打ち解けた相手だという事実によって、「あのときはどうも」と言葉を交わすだけでお互いの緊張や探り合いの段階を飛び越え、踏み込んだ話し合いをすることができました。
文化人類学で共食に触れていなかったら、「下戸は居心地が悪いから」とここまで飲み会に積極的に参加はしなかったかもしれません。他者を理解しようとする姿勢を文化人類学を通して学べたことは私の財産となっています。

3月旅行①:九重 前日の大雪がまだ残っていた
(麓には色んな種類の飲食店があったが、うどん屋がダントツの人気だった。)

3月旅行②:熊大近くのお店のチキンビリヤニ
(美味しいビリヤニがあるお店は珍しいということを、熊本を離れてから知って1年間焦がれた味…。)
店名:パンジャブレストラン

11月の旅行:東京上野のウイグル料理
(「ガチのウイグル料理」を提供するお店のLagman(具材のせ麺)とラムの串焼き、ピラフなど。ほぼ塩とクミンの味付けだけなのに、肉そのものの味が濃く、脂までとても美味しかった。)