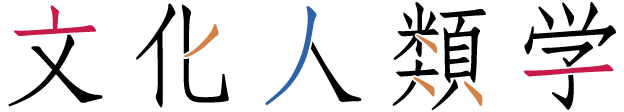しゃべり場
保険と文化人類学
みなさん、こんにちは!2024年3月に修了しましたダウランです。 今は損害保険会社で働いていて、社会人になってからあっという間に1年間が経ってしまいました。 保険と文化人類学は一見すると関係のない分野のように思えますが、実は意外とつながりがあるんです。 今の仕事では、直接お客さんに保険を売るのではなく、代理店を担当し、代理店を通じて保険を販売する「間接営業」を行っています。代理店ごとに扱う保険の種類や知識レベルが異なるため、それぞれに合わせた勉強会を開いたり、販売のポイントを一緒に考えたりすることが重要です。このように異なる背景を持つ代理店と接する際に、文化人類学で学んだ視点が役立っています。 また、場合によっては代理店と一緒に企業を訪問し、保険商品の提案を行うこともあります。その際、企業の状況や課題、リスクについて対話を通じて引き出し、最適な提案を考えることが求められます。このプロセスは、文化人類学で学んだ考え方に通じるものがあります。 さらに、損害保険の仕事では、「チャネル」と呼ばれる異なる販売経路が存在します。例えば、生命保険をメインに扱う代理店や、自動車関連の代理店など、それぞれが異なる客層を持っています。そのため、話す内容や伝え方を工夫する必要があります。こうした違いを理解し、それぞれに合った対応をすることに、文化人類学の学びが活かされていると感じます。 また、保険というものの考え方自体が、文化によって大きく異なります。例えば、日本では保険に加入して万が一の時に備えておきたいと考える人が多いですが、海外の一部の国では「保険は不要な出費」と捉えられることもあります。さらに、こうした文化の違いは国の違いだけでなく、同じ日本でも企業ごとの文化や価値観によって異なります。ある企業ではリスク管理の一環として保険を重視する一方で、別の企業ではコスト削減の観点から保険を最小限に抑えようとする場合もあります。こうした価値観の違いを理解し、お客さんに納得してもらえる説明をすることも大切な仕事の一つです。 文化人類学を学んだおかげで、仕事の中で柔軟な視点を持てるようになったと感じています。いろいろな考え方を受け入れ、相手に合わせた対応ができるのは、保険の仕事をする上で大きな強みになります。