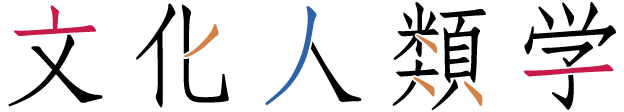研究室について
研究室紹介動画
ようこそ熊大人類学研究室へ
文化人類学は、ある事象を、その事象が発生した文化ないし社会の文脈から読み解いていく学問です。そこには自分にとっての従来の解釈からのみでは決して得られないような発見があることと思います。
対象となるフィールドもさまざまで、オタクから先住民族、科学者からヤクザ、家畜からペット、果ては微生物まで、あらゆる文化、社会の中に文化人類学的考察の可能性が存在しています。さらに、そこから得られた見識は、実は自分たちの「当たり前」にも共通している部分があることが往々で、ある事象に関するミクロな分析から人間一般に関するマクロな考察への飛躍を経験することこそが、文化人類学を学ぶ面白さであり、人間としての素養を磨く機会になることだと、つねに感じています。
このような壮大な地平を俯瞰する経験は、学問の世界においてのみではなく、きっとこの先の人生のさまざまな局面で、私たちに新たな視点をもたらしてくれると感じます。とくに、多様性への寛容さが叫ばれるこのご時世においては、まさに入り用だと思いませんか?
現在、熊大人類学研究室には十数人のメンバーがいます。メンバーたちは国籍、宗教、言語、年齢などバックグラウンドもさまざまです。こうしたメンバーとともに、ときには先生の主催する研究会などに参加し、ユニークなアイデアに出会い、知的な刺激を日々受けています。多様性を尊重し合い、切磋琢磨し合う気持ちのよい研究室において、学生生活を実りあるものにしましょう。
井三幸(2017年入学生)
2020年春
文化人類学履修モデルカリキュラム
| 学年 | 講義 | 実習 | 演習 | 卒業論文 | 学習内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 |
文化人類学 (文化人類学Ⅰ) |
文章作成演習 | 文化人類学の成り立ち、主な研究対象や方法を知り、その基本的な概念に触れます。 | ||
| 最前線の社会文化研究 | |||||
| 2年 |
社会人間学特殊講義A
(社会人間学特殊講義) |
社会調査法概説 | 社会人間学演習 | 文化人類学の基礎知識や調査方法、最新の研究動向について幅広く学習します。 | |
|
社会人間学特殊講義A
(文化人類学概論Ⅱ) |
|||||
| 3年 | 社会調査実習Ⅰ・Ⅱ | 課題研究Ⅰ・Ⅱ | 社会調査や文献講読を通じて文化人類学の専門性を強化しつつ、個人研究テーマの設定と研究方法について勉強します。 | ||
| 文化人類学演習 | |||||
| 文化人類学応用演習 | |||||
| 4年 | 課題研究Ⅲ | 卒業論文 | 研究テーマを絞り込め、データ分析しながら、先行研究批判を行い、卒業論文を完成します。 | ||
| 文化人類学演習 | |||||
| 文化人類学応用演習 | |||||
| 社会人間学応用演習 |
沿革
熊本大学文学部における文化人類学研究室の歴史は短いものの、全国的にみて組織として文化人類学の看板を掲げる数少ない研究室の1つであり、九州地域における人類学研究と教育の拠点の1つでもある。1993年(平成5年)、地域科学科に文化人類学講座が開設され、同年桜井哲男(民族音楽学、韓国研究)が、翌年池田光穂(医療人類学、ラテンアメリカ研究)がそれぞれ赴任した。1997年、桜井が阪南大学へ転出し、その後任として慶田勝彦(文化人類学、東アフリカ研究)が1998年に赴任した。2005年、池田が大阪大学へ転出し、その後任としてシンジルト(社会人類学、内陸アジア研究)が2006年に赴任した。2020年、慶田がコミュニケーション情報学科の教育および附属国際人文社会科学研究センターの業務を担当することになり、現在に至っている。
現在の文化人類学教室が誕生するまでにはさまざまな経緯があった。1997年、文化人類学講座は、地域科学科に所属していた民俗学講座とともに文化表象学という新しい講座に帰属した。文化表象学時代においては、学生はまず人類学と民俗学を学び、それから自分にあった専門を選択する方法を採用し、教室運営も両専門の教員4人によって行なわれていた。2005年の改組をうけ、人間科学科と地域科学科が合併され、総合人間学科が誕生した。そこでコースの再編により、民俗学と別れた文化人類学は、総合人間学科社会人間学コースの3つの履修モデルの1つとして再スタートした。更に、文法棟改築に伴い、2009年度からは、再び独立した研究室をもつようになった。
卒論
- 2024年度
- 2022年度
-
- eスポーツに関する人類学的研究――遊びとなりわい――
- 「個」をめぐる人類学的考察
- ホモセクシャル・クローゼットを描く――性的マイノリティの生きる技法に関する人類学的考察――
- フードロスに関する人類学的研究――熊本大学生協を事例として――
- 2021年度
-
- 熊本大学寄宿舎の民族誌的研究
- 食とスポーツの人類学的考察ーーお相撲さんはなぜふくよかなのかーー
- カザフスタンの「オラルマン」に関する人類学的研究日系ブラジル人との比較
- コムニタス論から見る装い
- 2020年度
-
- ペット葬儀の民族誌
- 2019年度
-
- 北欧サーミの故郷とは何か――映画Firekeepersと『サーミの血』を通して――
- 日本人の遺体へのこだわり――東日本大震災・日本航空123便墜落事故の死体処理に関する文化人類学的考察――
- モンタナ州における北米先住民族の現在地――ノーザン・シャイアンの語りを通して――
- 大坂なおみの揺れ動く新たな日本人/黒人像について
- 2018年度
-
- ボーンズ/BONES-Temperance BrennanとKathy Reichs ――ブレナンはもう一人のライクスといえるのか――
- 隣のムスリム ――熊大留学生におけるヒジャブの民族誌的研究――
- 中国のソフト・パワー ――欧米日における孔子学院の文化人類学的研究――
- 2017年度
-
- 「四国八十八箇所霊場と遍路道」における徒歩巡礼は宗教的なのか?
- 熊本地震と贈与
- 二つの『ゲド戦記』――アーシュラ・K・ル=グウィンと宮崎吾朗の比較――
- 料理とは何か―レヴィ=ストロースの『生のものと火を通したもの』から考える
- 憑依から見る変身の構造とその魅力
- 2016年度
-
- オノマトペの壁:越境するマンガについての人類学的研究
- 毛沢東の多義的な位置づけに関する人類学的研究
- 2015年度
-
- 写真は〈現実〉を切り取ることができるか
- 上橋菜穂子が紡ぐ「他者と共に生きる物語」:「守り人」シリーズにおける異界が表すものは何か
- ウィリアム・ジェイムズと「二度生まれ」:我々の生きる現代の宗教的諸相とはどのようなものか
- 「奇妙なもの」との向き合い方:ボーカロイド初音ミクを事例として
- ドイツ生まれのトルコ系移民:文化リテラシーとイスラーム
- 2014年度
-
- マスクとリスク:現代日本におけるマスク着用の習慣はリスク儀礼と言えるか
- 性的名誉の多重性:現代トルコにおけるナムスの人類学的研究
- マルセル・モースの『贈与論』の射程と現代的意義:返礼義務としてのホワイトデーと日本的「負い目」の意識
- ボクサー具志堅用高と笑い:トリックスターと「ガージュー」の両義性
- 魂送りの人類学的考察:極東ロシア狩猟民社会にみる人獣関係の一側面
- 2013年度
-
- 商品としてのボランティア活動:フィリピン・マニラにおけるボランティアツアーを事例として
- 現代のデモと集合的沸騰:金曜官邸前抗議と在特会のヘイトスピーチを事例として
- 世界遺産「富士山」と葛飾北斎:葛飾北斎の『富嶽三十六景』が有する顕著な普遍的価値とはなにか
- 味の素とグローバリゼーション
- ユネスコ無形文化遺産と文化的多様性:「和食」の登録を事例として
- 2012年度
-
- 再建されたトーテム・ポール:北西海岸におけるモノ、自然、社会
- フィールドワークと録音:『サバンナの音の世界』にみる録音の有用性
- 民族境界の越え方:中国の計画出産政策を利用する人たち
- 2011年度
-
- 哈日族のなり方:経済的集団がつなぐ日台関係
- カンボジアの絵絣ピダン:「もの」としてのはたらき
- 国分拓のヤノマミ表象:人々はなぜドキュメンタリー『ヤノマミ』に惹かれたのか
- 日本におけるトランスジェンダーの認識と受容:メディアによってつくられた光と影
- 韓国の仮面:風刺が形成した社会
- 刺青の両義性:明治期における刺青のあり方
- ジミ・ヘンドリックスとエレクトリック・サウンド
- 2010年度
-
- 死から考える共同体:新疆ウイグル自治区のケースにおいて
- マンガの伝播がもたらすもの:台湾の事例を中心に
- 真正性にこだわる訳:観光人類学の視点から
- ランタンフェスティバルが語るもの:新地華僑社会における集団と個人のあり方
- 他者を構成するもう一つのまなざし:女子割礼を中心に
- 2009年度
-
- 在日コリアンサッカーの越境性:スポーツ人類学の視点から
- フェアトレードに関する経済人類学的考察
- 秋祭りの社会的機能:天草下浦町の民族誌
- 水商売女性の民族誌:熊本市「スナックX」の事例を中心に
- 不浄観念の力学:ジプシーにおける動物の位置づけ
- ネット・ナショナリズムに関する文化人類学的一考察:中国のコンテクストにおいて
- ルワンダにおける「和解」の現在:ガチャチャ・家造り・カゴ作りを事例に
- 2008年度
-
- リアリズムとしての山下敦弘映画:現実から引き出されるエンターテイメント
- 「樹木葬」現象をめぐる民族誌的考察
- ギャングスタ・ラップを通して見る現代アメリカ
- 映画規制における映画作品の役割
- 見えない世界への旅:星野道夫とアラスカとの出会いを中心として
修論
進路
- 公務員
-
- 佐賀県警
- 鹿児島県警
- 財務省福岡財務支局
- 北九州市役所
- 久留米市役所
- 別府市役所
- 飯塚市役所
- 佐賀地方検察庁
- 法人職員
-
- 九州大学
- 佐賀大学(図書館司書)
- 民間企業
-
- 三井住友海上火災保険株式会社
- (株)大日本印刷
- (株)カゴメ
- (株)ジャパネットたかた
- (株)JR九州ビルマネジメント
- (株)九州カード
- (株)ヒライ
- 朝日生命保険
- (株)エスケーホーム
- 熊本製粉株式会社
- (株)システムフォレスト
- (株)明和不動
- 大学院進学
-
- 熊本大学大学院
- 関西学院大学大学院
- 一橋大学大学院