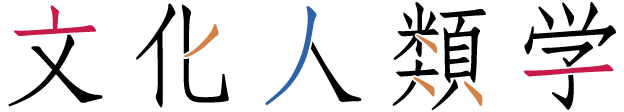教員
現地調査
中国青海省黄南チベット族自治州河南モンゴル族自治県
1990年代に比べて河南蒙旗ではほとんど羊肉が食べられなくなりました。
それは、ヤクの数が増え、羊が減ってきたからだと言われています。羊の数が減ったのは、狼が増えたからだと言います。
そして、狼の数が増えたのは生物多様性の保全のためだと理解されています。
そこで、牧畜民たちは、狼に強い種として、ヤクという家畜の飼育、さらに最近では、野生ヤク(アムドチベット語で、「ジョン」)の種を導入し、ヤクの群れにおける野生種の割合を高めていくべく、知恵を絞り、財力を投入しています。
結果、人間が狼を増やし、狼は羊を減らし、ヤクを増やし、その野生化を促進させている、というような連鎖が生まれています。
もしかしたら、この「人間―狼―家畜の野生化」の連鎖は、人間(文化)のため急増した狼(自然)とはなにか?家畜(文化)とは何か?野生(自然)とは何か?文化と自然を二分しその安定的な分類基準をもつ人間などは本当にいるのか?といったことを考えさせる契機となるのかもしれません。
 1 羊の数が年々減っています
1 羊の数が年々減っています 2 馬にとって代わっているのは4WD
2 馬にとって代わっているのは4WD 3 食事の前に手を洗うのはどこの習慣?と聞かれながら黙って手を洗う私
3 食事の前に手を洗うのはどこの習慣?と聞かれながら黙って手を洗う私 4 ヤクに乗るかかし。移動するかかしをみて、かかしは農耕社会のものだ信じ込んできた私には新しい課題が生まれました
4 ヤクに乗るかかし。移動するかかしをみて、かかしは農耕社会のものだ信じ込んできた私には新しい課題が生まれました 5 十数年前、信じられないくらい高価でしたが、近年市場価値が一気に低下したチベタン・マスティフ。今も昔も、牧畜民の「友」です
5 十数年前、信じられないくらい高価でしたが、近年市場価値が一気に低下したチベタン・マスティフ。今も昔も、牧畜民の「友」です 6 幼いことから飼われている野生のメスヤク(ジョン・モ)の乳を搾る牧畜民
6 幼いことから飼われている野生のメスヤク(ジョン・モ)の乳を搾る牧畜民 7 野生のヤクをうまく飼育できていることを自負する牧畜民ご一家
7 野生のヤクをうまく飼育できていることを自負する牧畜民ご一家 8 家畜のメスヤク(ジ)に発情する野生ヤクの種雄(ジョン)。野生のヤクの種がほしく、家畜のヤクの種雄を一切飼わない世帯もあります
8 家畜のメスヤク(ジ)に発情する野生ヤクの種雄(ジョン)。野生のヤクの種がほしく、家畜のヤクの種雄を一切飼わない世帯もあります 9 野生のヤクの気性が荒いというのがよくある認識です。しかし、それは誤認であり、飼い主の性格、育て方によって、野生のヤクも変わるのだと、経験的に語る牧畜民も多くいます
9 野生のヤクの気性が荒いというのがよくある認識です。しかし、それは誤認であり、飼い主の性格、育て方によって、野生のヤクも変わるのだと、経験的に語る牧畜民も多くいます 10 野生のヤクが純粋に好き!という牧畜民も多くいます。野生のヤクの写真を撮影するのが大好きなTB氏が、自慢の写真を私に見せてくれました
10 野生のヤクが純粋に好き!という牧畜民も多くいます。野生のヤクの写真を撮影するのが大好きなTB氏が、自慢の写真を私に見せてくれました 11 河南蒙旗のヤクのブランドとなる「ホド」という品種のヤクを大規模飼育する農場の主(左)は、相撲取りの名人であると同時に映画出演の経験の持ち主でもあります
11 河南蒙旗のヤクのブランドとなる「ホド」という品種のヤクを大規模飼育する農場の主(左)は、相撲取りの名人であると同時に映画出演の経験の持ち主でもあります 12 羊の肉はほとんど食べられなくなりましたが、脂肪(黄色部分)まで歯ごたえのあるヤクの肉の味は濃厚でおいしいです。ヤクの肉にはもう飽きたという人と私は出会ったことがありません
12 羊の肉はほとんど食べられなくなりましたが、脂肪(黄色部分)まで歯ごたえのあるヤクの肉の味は濃厚でおいしいです。ヤクの肉にはもう飽きたという人と私は出会ったことがありません