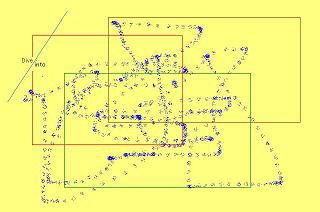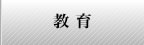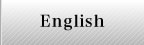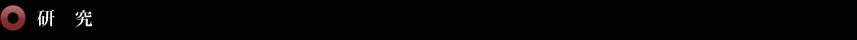研究分野
社会学、とくに国際社会学、文化社会学、理論社会学
研究テーマ
- 国際社会学領域 : 国際人口移動研究、移民研究
・フランスおよび日本を主なフィールドとした、国境を超える人の移動、移民の集合行為や社会統合の理念と政策などについての研究。
・フランスの旧植民地(とくにアルジェリア)の脱植民地化およびそれにともなう人の移動と社会の再編についての研究。
- 文化社会学領域 : 記憶の社会学
・三池炭鉱をはじめとする産業遺産をフィールドとして、社会的記憶の研究。
研究のキーワード
国際人口移動、排除と統合、 グローバル/ナショナル/ローカル、記憶、産業遺産、近代化遺産、コンフリクト、不確定性、近代/現代
業績一覧
単著
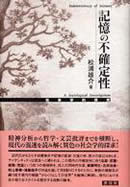 |
『記憶の不確定性―社会学的探求』 東信堂、2005年 |
共著
 |
『帝国以後の人の移動―ポストコロニアリズムとグローバリズムの交錯点』蘭信三編、勉誠出版、2013年 |

| 『中国残留日本人という経験-「満州」と日本を問い続けて』蘭信三編著、勉誠出版、2009年 (担当:「ピエ・ノワールとは誰か?―フランスの植民地引揚者のアイデンティティ形成」)568-593頁 |
 |
『多元的世界における寛容と公共性』芦名定道編著、晃洋書房、2007年 (担当:第10章「差異の共和国―フランスにおける多文化主義の受容をめぐって」182-197頁) |
 |
『「近代」と「他者」』伊藤洋典編、成文堂、2006年 (担当:第4章「現代フランスの宗教と公共性―異文化間コンフリクトとしてのスカーフ問題」 91-117頁) |
 |
『村上春樹スタディーズ』今井清人編、若草書房、2005年 (担当:第9章「個人化の時代における寛容のかたち―村上春樹と他者への態度」205-234頁) ※1 下記の《報告書》欄にある同名論文を再録 ※2 高校用国語教科書『新精選国語総合』(明治書院)参考資料教材に使用 |
論文
- 「炭鉱(ヤマ)の声を聞く―熊本大学文学部の社会調査実習」『社会と調査』第12号、90-95頁、2014年(慶田勝彦との共著)
- 「都市暴動の社会学」『日仏社会学会年報』第24号、75~88頁、2013年
- 「記憶と文化遺産のあいだ―三池炭鉱の産業遺産化をめぐって」『西日本社会学会年報』No.11、37-50頁、2013年
- 「タルコフスキーと近代の廃墟」『Becoming』No.31、3-21頁、2013年
- 「産業遺産と文化のグローバル化」/《 Patrimoine industriel et la globalization de la culture 》 『日仏社会学会年報』第22号、
83~103頁、2011年 - 「オルハン・パムクとイスラム主義の声―『雪』における」『Becoming』No.25、44-72頁、2010年
- 「社会運動から都市暴動へ―フランス郊外における集合行為の変容について」
『日仏社会学会年報』 第19号、15-28頁、2009年 - 「脱植民地化と故郷喪失―ピエ・ノワールとしてのカミュ」『Becoming』No.13、3-34頁、2006年
- 「フランスにおける国民戦線の台頭と社会システムの変容」『文学部論叢』65号、23-44頁、2005年
- 「反復する身体―古井由吉における記憶と生」『京都社会学年報』第12号、73-90頁、2004年
- 『記憶の社会学―現代の不確定性について』
(京都大学大学院文学研究科平成15年度博士課程学位論文)、2004年 - 「忘却と笑い―後藤明生における記憶と生」『ソシオロジ』146号、37-54頁、2003年
- 「記憶の不確定性―フロイトとベルクソン」『現代社会理論研究』12号、14-25頁、2002年
- 「知と信の社会理論―『宗教生活の原初形態』における」
『社会学評論』51号No.1、2-19頁、2000年 - 「実証主義の諸問題―認識論的批判とその存在論的意味」
『ソシオロジ』134号、13-34頁、1999年 - 「社会科学の臨界点」『京都社会学年報』4号、177-188頁、1996年
報告書
- "The Historical Formation of Pieds-Noirs : Collective identity of repatriates from Algeria to France", Terada(ed), Acculturation dans les époques d'internationalization, L'Association d'études de l'acculturation & L'École post-universitaire des sciences sociales et culturelles, Université de Kumamoto, pp.45-54, 2007
- 「個人化の時代における寛容のかたち―村上春樹と他者への態度」
京都大学21世紀COEプログラム報告書Ⅲ(哲学篇2)
『グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成』63-85頁、2004年 - 「日常の記述/異文化の理解―あるケニア人留学生の生活」
京都大学留学生研究会編『ライフ・イベント 語られる留学』75-88頁、1999年
教科書
 |
『〔全訂新版〕現代文化を学ぶ人のために』井上俊(編)、世界思想社、2014年 (担当:第5章「文化と権力」81-96頁、キーワード解説「マルクス主義の文化論」249-250頁) |
 |
『文化社会学入門』井上俊・長谷正人編著、ミネルヴァ書房、2010年 (担当:「文化と権力」、208-211頁) |
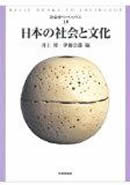 |
『社会学ベーシックス 第10巻 日本の社会と文化』井上俊・伊藤公雄編、世界思想社、2010年 |
 |
『歴史社会学のフロンティア』筒井清忠編、人文書院、1997年 (担当:第13章「アーネスト・ゲルナー『ネイションとナショナリズム』」103-108頁) |
その他
- 書評:G・ノワリエル『フランスという坩堝』『図書新聞』3242号、2016年2月13日
- 書評:木村至聖『産業遺産の記憶と表象-「軍艦島」をめぐるポリティクス』『社会学評論』263号66巻3号95、2015年12月
- 短文:「『寄生獣』あるいは野生の寛容」公益財団法人たばこ総合研究センター『TASC MONTHLY』No.477、13-19頁、2015年9月
- 書評:「日常生活文化という視座が引揚げ研究にもたらすもの」『関西学院大学先端社会研究所紀要』第12号、98-103頁、2013年3月(書評対象:島村恭則(編)『引揚者の戦後』新耀社、2013年)
- 短文:「異文化をめぐる冒険」一般社団法人 社会調査協会ホームページ「たのしい社会調査」エッセイ、2015年4月(慶田勝彦との共著)
- 書評:竹内洋『メディアと知識人―清水幾太郎の覇権と忘却』(中央公論社)(熊本日日新聞2012年9月2日)
- 短文:「きたないはきれい―近代の廃墟の遺産化/審美化をめぐって」『世界思想』39号、9~12頁、2012年
(2013年度 大分大学、明治大学、金城学院大学、京都外国語大学、神戸女学院大学、三重大学、琉球大学、2014年度 北九州市立大学、関西大学、高知大学の入試問題に使用) - 公開講座「多文化時代を考える」熊本大学高大連携推進プロジェクト
「高校生のための熊大ワクワク連続講義」(於 熊本大学)、2011年10月、2012年11月 - 短文:「アルキとは誰か―フランスにおけるもう一つの『引揚者』問題」『アジア遊学』第145号、勉誠出版、237-245頁、2011年
- 名古屋大学日本近現代文化研究センター主催シンポジウム「反乱する若者たち―1960年代以降の運動・文化」新世代パネル「<反抗者>たちとその系譜―Singularité et Universalité」ディスカッサント(於 名古屋大学、愛知)、2010年1月
- 書評:竹内洋『学問の下流化』(中央公論新社)(熊本日日新聞2008年11月23日)
- 短文:「書評に応えて」(『記憶の不確定性』)『ソシオロジ』52(2),122-125頁
- 短文:「失われた記憶を求めて」(津田睦美ビジュアルアート作品展
《 Le fer à cheval 》 於 九州日仏学院 のテキスト)、2007年 - 短文:「フランスの植民地引揚者たち―アルジェリアの場合」
『アジア遊学』第85号、勉誠出版、182~186頁、2006年 - 書評:竹内洋・佐藤卓巳(編)『日本主義的教養の時代』(柏書房)
(熊本日日新聞2006年3月19日)
主な口頭発表
- 「フランス引揚げ研究の現状と課題」(於 琉球大学)、2016年3月
- 「炭鉱と記憶」全国石炭産業関連博物館等研修交流会(於 芽が出た根、福岡県大牟田市)、2015年10月
- 「記憶の場を飼い慣らす」シンポジウム「創造的接合知生成のための日常人類学的研究 文化から日常へ――ソフトレジスタンス・実践・創造的接合知」(於 京都大学)、2015年3月
- "Industrial Heritage and Memory - A case of Miike coal mine", XVIII ISA World Congress of Sociology, RC16 Sociological theory 295 : "Theorizing Legacy : Does the Past Have Power over Political Events"(於 パシフィコ横浜、神奈川)、2014年7月
- 「都市暴動の社会学」分身の会(於 ともいき荘、京都)、2013年9月
- 「アルキの『帰還』とフランスのポスト植民地主義」研究会「帰還移民の比較民族誌的研究―帰還・故郷をめぐる概念と生活世界」(於 国立民族学博物館、大阪)、2012年7月
- 「記憶と遺産のあいだ―三池炭鉱の場合」西日本社会学会大会シンポジウム「社会的現実の変容と記憶の問題―〈記憶の社会学〉の可能性を問う」(於 鹿児島大学、鹿児島)、2012年5月
- "Crossing the dividing line ? -Algerian auxiliaries of French army during the Algerian War-`、科研費研究会(於 上智大学、東京)、2012年3月
- 「アルキと『引揚げ』の記憶」科研費研究会(於 上智大学、東京)、2011年11月
- "Patrimoine industriel et la glocalisation" 日仏コローク(於 フランス・パリEHESS)、2011年10月
- 「タルコフスキー映画における廃墟イメージについて」分身の会(於 ともいき荘、京都)、2011年6月
- 「フランス都市暴動を考える」(於 上智大学、東京)、2009年12月
- 「フランス都市暴動における暴力の諸相」日仏社会学会大会シンポジウム「パースペクティヴとしての<力>―暴力・労働・贈与」(於 岡山県立大学、岡山)、2009年10月
- 「宗教・政治・文学―オルハン・パムク『雪』における他者の声」分身の会(於 京大会館、京都)、2009年3月
- 「都市暴動の論理」日本社会学会(於 東北大学、宮城)、2008年11月
- 「ハルキとフランスのポスト植民地主義」科学研究費研究会(於 上智大学、東京)、2008年10月
- 《 Logique des émeutes urbaines en France 》(於 パリ国際大学都市日本館、フランス)、2008年7月
- 「差異の共和国―フランスと多文化主義」COE研究会「多元的世界における寛容性についての研究」(於 京都大学、京都)、2006年7月
- "Historical formation of Pieds-Noirs" 日仏国際ワークショップ(於 熊本大学、熊本)、2006年10月
- 「ピエ・ノワールとは誰か?―フランスにおける植民地引揚者のアイデンティティ形成」科研費研究会(於 京大会館、京都)、2006年10月
- 「ピエ・ノワールの歴史的形成」日本社会学会(於 立命館大学、京都)、2006年11月
- 「脱植民地化と故郷喪失―ピエ・ノワールとしてのカミュ」分身の会(於 京大会館、京都)、2005年11月
- 「寛容と無関心のあいだ―村上春樹をめぐって」COE研究会「多元的世界における寛容性についての研究」(於 京都大学、京都)、2003年9月
- 「ミステリー小説における記憶喪失のモチーフ」日本社会学会(於 大阪大学、大阪)、2002年11月
- 「アルヴァックスの集合的記憶論」日本社会学会(於 一橋大学、東京)、2001年11月
研究プロジェクト
- 科学研究費補助金・基盤研究(C)「旧産炭地における産業遺産と地域再生ー日本・フランス・イギリスの国際比較研究」(研究代表者) 2015-2017年度
- 社会調査協会 社会調査実習(G科目)助成金 2013年度および2016年度
- 科学研究費補助金・基盤研究(A)「二〇世紀東アジアをめぐる人の移動と社会統合に関する総合的研究」(研究分担者)(研究代表者:蘭信三 上智大学教授) 2013-2017年度
- 日本証券奨学財団研究調査助成金「非定住型外国人労働者受け入れ制度の再検討-熊本県の研修生・技能実習生の実態調査から」 2011-2013年度
- 科学研究費補助金・若手研究(B)「フランス都市暴動の社会学的研究-集合的行為論と社会的排除論の観点から」(研究代表者) 2009-2011年度
- 科学研究費補助金・基盤研究(B)(1)「日本帝国崩壊後の人口移動と社会統合に関する国際社会学的研究」(研究分担者)(研究代表者:蘭信三 上智大学教授) 2008-2011年度
- 熊本大学海外研修助成制度 2007年度
- 科学研究費補助金・基盤研究(B)(1)「エスニック・マイノリティの社会参画と国民国家の社会統合に関する比較社会学的研究-中国帰国者およびエスニック移民の比較研究を中心として」(研究分担者)(研究代表者:蘭信三 京都大学助教授) 2004-2006年度