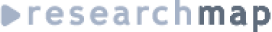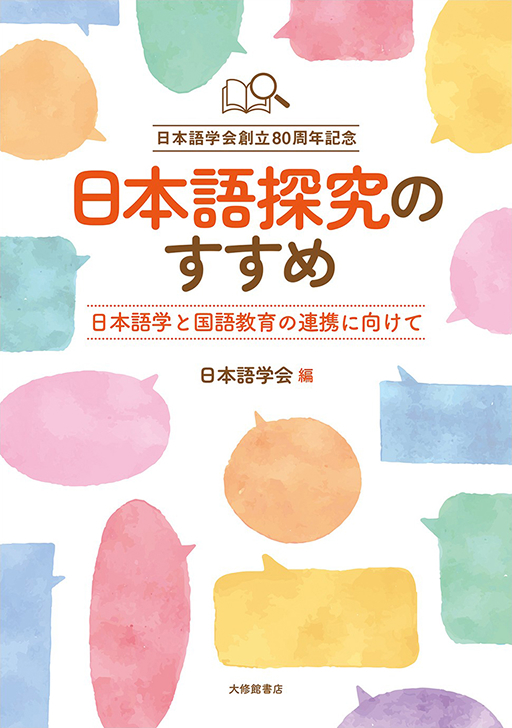
この本に関わった教員
茂木 俊伸
Toshinobu MOGI
教員の情報についてはリンク先の
「researchmap」をご覧ください
日本語探究のすすめ
日本語学と国語教育の連携に向けて
ひとこと紹介
日本語学会が主催する「中高生日本語研究コンテスト」は,中高生が取り組んだ日本語探究の成果を動画にまとめて発表するイベントです。
本書は,同コンテストの解説本として日本語学会の創立80周年記念に出版されました。
私は同コンテストの立ち上げに委員として関わったのですが,日頃の大学の授業でも学生に日本語観察を勧めています。その面白さを「研究」の形でまとめるためのノウハウを,本書の第1部「日本語を探究すること」に書きました(共同執筆)。
日本語に関心のある中高生の皆さんや指導者の先生方のお役に立てば幸いです。
主要目次
- 第1部 日本語の探究
- 日本語を探究すること
- 【探究事例1】おかしみはどこから来るのか―漫才の会話体系の分析
- 【探究事例2】聞き取りやすい日本語
- 【探究事例3】日本語と日本手話のずれ
- 【探究事例4】古典学習と地域方言の関連性についての研究
- 【探究事例5】外国人児童生徒の家庭内における言語使用―我が家の場合
- 【探究事例6】オノマトペを数的に食べる
- 【探究事例7】中学生からの挑戦状―「押す」と「突く」の違いを見分けろ!
- 【探究事例8】「ものづくし」における修辞・技巧的表現の研究 北原白秋、金子みすゞはそれぞれどのように「ものづくし」に当たる表現法を活用したか―近代詩における「ものづくし」研究
- リサーチ部門最優秀賞受賞者インタビュー
- 第2部 日本語学と国語教育の連携に向けて
- 第1章 日本語研究室から国語教室へ
- 第2章 日本語学から見た国語教育との連携
- 第3章 国語教育から見た日本語学との連携
- 第4章 国語科教育学における日本語学研究の実践的展開
- 第5章 学習指導要領と日本語学
- 第6章 中高教員が日本語学に期待すること
- 第7章 日本語学を発展させる、中高生の研究
- 第8章 国語学・日本語学研究史と国語教育
- 第9章 解釈と結びつく文法―国語教育と日本語学との接点として
- 第10章 教育科学研究会・国語部会の言語教育(日本語指導)について―文法教育を中心に
- 第11章 多様な子どもたちが学ぶ「国語」に日本語学ができること
- 第12章 日本語研究者の問題意識を教育現場と共有するには
- 第13章 日本語学の知見を活用して国語の授業をつくる―日本語学を教材研究に役立てる
- 第14章 表現と理解の往還をつなぐ「言語事項」の学習
- 第15章 高等学校での古典語探究のすすめ
※ 詳細な目次は出版社のページでご確認ください。